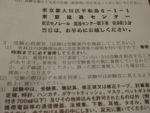こんにちは。YUMAです。 遊んでばかりいますが、合間を縫って勉強もしています。簿記論と財務諸表論の2科目受験です。…
【酒税法】粉末酒の換算係数とはなんぞや?なぜあの式になるのか

こんにちは。YUMAです。
今年の税理士試験は財務諸表論と酒税法の2科目を受験しようと思っています。
財務諸表論は過去に受験しているので勝手は分かっているのですが酒税法は初の受験です。
今はとりあえずTACの問題集を使って計算問題を勉強しています。
計算問題を解いてる中で、「なんじゃこりゃ?」と思った点があり、なんとか自分で理屈をつけたことがあるのでメモしておきます。
粉末酒の数量計算の部分です。
粉末酒の問題例
-資料-
溶解してアルコール分1度以上の飲料とすることができる粉末状の酒類
と、こう来たら判定としては「粉末酒」だなと。これは誰でも分かります。税率は1kLあたり390,000円だよねと。
問題はこのあとの数量計算です。
容器の容量=300g、 ケース=10袋
↑こんな感じで問題が出ます。
他の酒類は全て「体積」であるリットル単位で数量が計算できるのですが、粉末酒は特殊で、「重量」であるグラム単位で表示されます。
なので、これを重量から体積に変換する必要があるわけです。
そのための資料として、
(粉末酒の)重量30.5gを蒸留水70.5gに溶解した場合の温度15度における比重は1.080である。
みたいなものが与えられます。
模範解答例
で、模範解答を見ると、
換算係数の計算
$$\frac{30.5g + 70.5g×(1-1.080)}{30.5g ×1.080}=0.75 (小数点第2位未満切捨)$$
$$0.3kg×10袋×0.75=2.25L=0.00225kL$$
と、このように「換算係数」というのを重量に掛け算すると体積に変換することができます。
ただ、換算係数の計算はなんじゃこりゃ?ですよね。
ここについて何も説明がないので困っていたわけです。
なぜ換算係数がこの計算式になるのか解明
少し考えて自分なりに納得しました。
(粉末酒の)重量30.5gを蒸留水70.5gに溶解した場合の温度15度における比重は1.080である。
「比重」というものが問題に与えられています。比重とは密度とほぼ同じ概念です。
簡単に言えば「体積あたりの重量」です。比重が1.5の物質は1Lで1.5kgの重さがあるということです。
水の比重は1です(小学校か中学校で習いましたね)。
問題に戻ると、粉末酒を蒸留水に溶かしてお酒にするわけです。登場人物は「粉末酒」と「蒸留水」の2つのみ。
ここで分かりすく、粉末酒の重量をF[kg]、体積をf[L]とします。
同じく蒸留水の重量はW[kg]、体積をw[L]とします。
大文字が重量、小文字が体積です
そうすると、水に溶かした粉末酒というお酒の比重は1.080ですから、体積当たりの重量を計算するには、重量÷体積で、
$$\frac{F+W}{f+w}=1.080$$
となります。
ここで、粉末酒の体積fと重量Fってなに?という話です。
これはまさに換算係数を用いてつなげられているものでした。重量を体積に換算するために掛け算するものが換算係数。
なので、換算係数をaとすると、$$a×F=f$$という関係になります。
ちなみに水の比重は1なので$$w=W$$です。
そうすると先ほどの比重の計算式は、
$$\frac{F+W}{f+w}=\frac{F+W}{aF+W}=1.080$$
となります。この式をaについて整理すると、
$$a=\frac{F+W×(1-1.080)}{1.080×F}$$
となります。
これでようやく、なんであんな計算式になったのか分かりました。
理屈を知っておけば、忘れてもすぐ導けるので簡単ですね。丸暗記は不要。
それではまた。